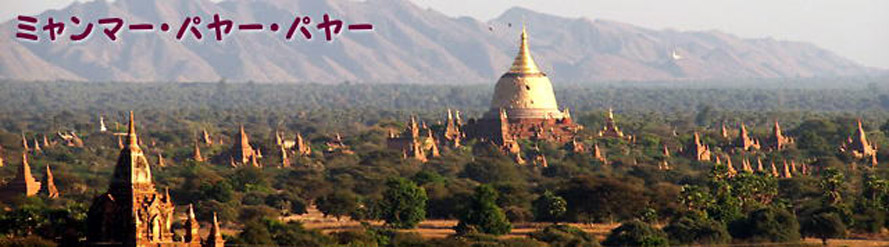 |
|
マンダレー近郊(1) <8日目(1月14日)>8時半、観光スタート。
マハムニ・パヤーの後は、一路アマラプラへ。目的地はマハーガンダーヨン僧院。ここでは1500人の僧侶が修行生活をおくっており、10時15分から大きなホールで僧侶が一斉に食事をするのだが、その見学が可能で(僧院側は歓迎しているとのこと)、このあたりの観光資源となっている。僧院側がなぜ観光の対象になることを歓迎しているのかは、想像するに、旅行会社からの寄付が期待できるからというような気がする。ミャンマーでは寺院に様々な寄付を行っている企業が多いようだが、それは旅行会社も同じと思われる。僧院での食事の様子を観光客に公開すると、旅行会社がそれにより観光客を自社のツアーに参加させるための材料にすることができる。そして、そうして得た利益の一部が寄付という形で、僧院に還元されるという仕組みなのではないだろうか?(ただの想像ですが) アマラプラに着いたのが少し早く、僧院の食事まではまだだいぶ時間があったので、近くの寺院によった(名前は?)。仏像だらけだった。
|





























