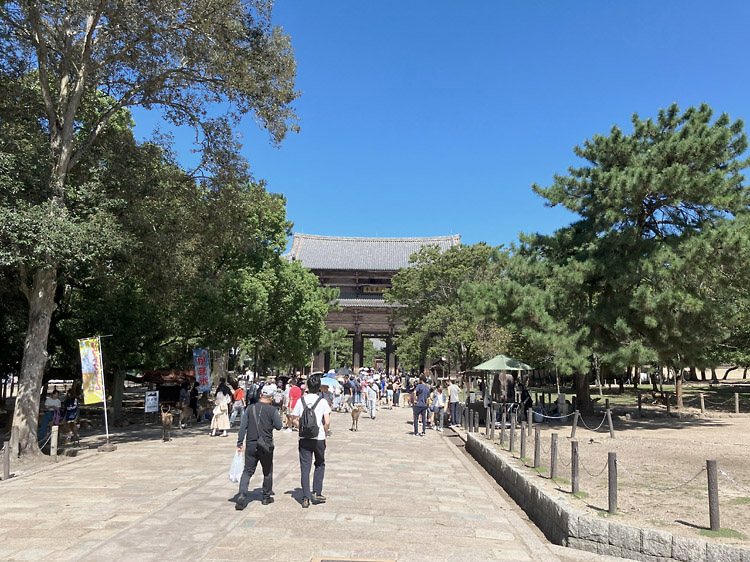| 奈良散歩(2024.09) |
| <母が訪れた場所を訪ねる旅> 母のアルバムに奈良のとあるお寺にある立派なソテツの木の写真があり行ってみたいと思った。 お寺の名前はわからなかったが、ネットで検索するとすぐに浄教寺という寺であることがわかった。 浄教寺の本堂は昭和戦前期に焼失しており、その後再建に着手、1968年に竣工。山門は幕末期に建設されたもので、それなりに古い建築物だが、有名な文化財が沢山ある奈良にあってはまったく目立たぬ存在だ。 しかし、本堂の前にある立派なソテツのお蔭で隠れた名所になっているようだ。浄教寺のホームページによると樹齢300年余りとのことで、写真にある通り一つの株から多く一つの幹が出ている。九州とかならば珍しいというほどでもないのかもしれないが、浄教寺は奈良のお寺であり、珍しい感じがする。 それから、ここ浄教寺本堂では、日本の古美術復興に力を尽くしたフェノロサが、1888年、日本の仏教美術の素晴らしさを説き、その保護の重要性をうったえる「奈良ノ諸君ニ告グ」という講演を行っている。 母は友人との奈良へ行った際、この寺を訪れているが、浄教寺について調べて訪れたとは思えない。宿泊したホテルから近いということで立ち寄ったのだと思うが、よい場所に行ってくれていたと思う。母が残した写真を見なければ、自分がこの寺について知ることはなかっただろうから。 例によって天気予報サイトを見て、酷暑がおさまってきたこと、雨にたたられることがないことを確認したうえで、飛行機の空席状況をみると、幸い席に余裕があったので奈良へ行くことにした。日程は1泊2日。ちょっと大規模な散歩という感じである。 9月、秋のお彼岸を過ぎた某日、新千歳空港を昼頃出発する便に搭乗して14時半ころ関西空港到着。16時20分ころJR奈良駅に到着後、その足で三条通りを歩き目指す浄教寺へ向かった。
<2日目> ホテルをチェックアウトして奈良町をブラブラしつつ元興寺へ向かった。母の写真のなかに「元興寺」の額のかかった門の前で撮った記念写真があったので行くことにしたのだけれど、何も調べずに行ったものだから大きなミスをおかしてしまった(それについては後述)。 元興寺の前身は飛鳥寺(法興寺)でもともとは蘇我氏の氏寺として飛鳥の地で創建されたお寺だが、平城遷都に伴い平城京に移転され寺名は元興寺と改められた。南都七大寺の一つに数えられ国家的な大寺院として栄えたが律令国家の衰退にともない平安時代には衰退した。ただ、平安時代中期以降の浄土教の流行にともない浄土信仰の場として栄え寺院としての命脈が保たれたとか。
さらに少し歩き元興寺北門に到着。
元興寺を一通り見学したのだが、母が記念写真を撮った「元興寺」の額を掛けた門がない。それもそのはず、古い元興寺の寺域内(かなり広い)にもう一か所「元興寺」があったのだ。そちらには塔の跡などの礎石が残っていて、母の記念写真はそちらで撮ったものだったのだ。何も調べずに行ったものだからミスってしまった。しかし、今回訪れた元興寺で見落とした瓦なども確認しに行かねばならないので、また訪れればよい。 帰りの飛行機までは時間がだいぶあるので、中心部から少し離れたところにある般若寺という寺へ行くことにした(少し距離があるので県庁前からバスを利用)。 般若寺は奈良時代に聖武天皇が平城京の鬼門を守るため『大般若経』を塔の基壇に収め卒塔婆を建てた寺で、般若寺の名は『大般若経』という経典の名前がもとになっているとか。 平安時代には学問の寺として栄えたが、源平合戦の際、平氏による「南都焼討」にあい伽藍は廃燼に帰した。その後、鎌倉時代に叡尊や良恵によって復興された。現在では花の寺として有名。
終わり。 |